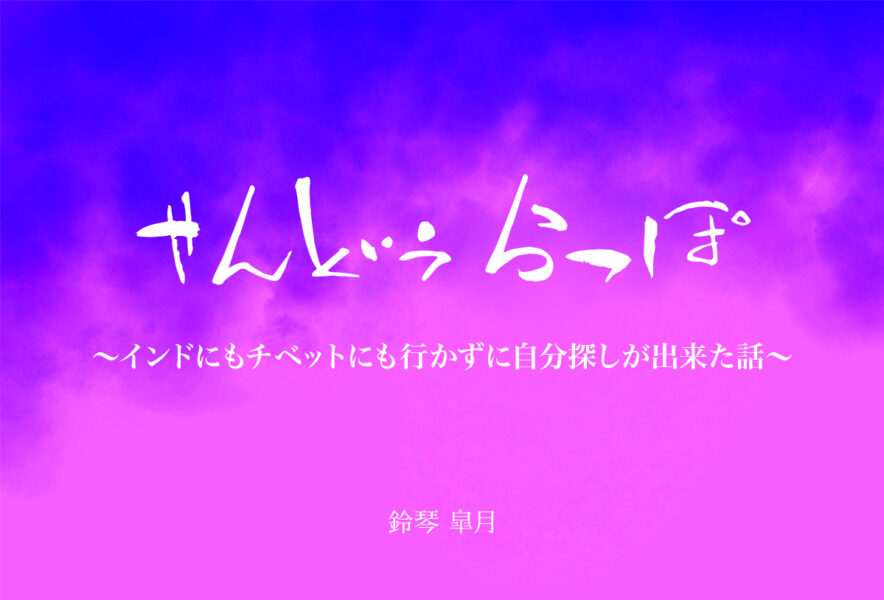固まってしまった永島を見つめながら、桃は話を続ける。
「『一流のプロ野球のバッターでも7打席は失敗してるねん』て話を例えで出さはる若社長さんみたいな人たまにいてはるけど、『それとこれは一緒なんか?』ていつも疑問に思てんねん。
あの人らはホンマは全打席ヒットの10割バッターを目指して、血のにじむような努力と綿密な準備を重ねて打席に立ってはるやん。それでもヒットになるのが結果3割やゆう話やんか」
「うちの会社がやってる飛び込み営業って・・・」
桃の言葉を受けて、永島が放心したようにつぶやいた。
「聴いた限り、そんな準備して打席に立ってるようには思われへんよな」
「まったくしてません」
「ビルの上から下まで手当たり次第訪問していくってゆうてたもんな」
「その通りです」
「な。迷惑や思うやろ」
「返す言葉がないです」
永島がうなだれる。
桃はさらに続ける。
「まだそこの会社のことを調べて『お宅の会社はここが弱いのでわが社のこの商品を使えばもっと利益が増えますよ』ゆうて提案でもしてくれるゆうんならまだしもやけどな」
「それやと少なくとも準備はしてますもんね」
「まぁでも突然アポもなしに訪ねてきて、誰かな思たら色黒の小太りな不法入国者みたいなんが『なんでもやりますよ』て繰り返すて、通報されても文句ゆわれへんけどな」
「またちょいちょい悪口がまざってます」
「おおっ、いつの間に!」
張り詰めていた空気がやっと和んだ。
桃のモットーでもある“緊張と緩和”のおかげだ。
「でもホンマですね。僕の場合は準備なんかなんもしてませんもんね」
「まぁちなみにちゃんと調べてきて提案してくれたとしても『大きなお世話じゃ!』ゆうて追い返すけどな」
「追い返すんかいっ!」
わたしが間髪入れずにつっこんだところで、やっと場に笑顔が戻った。
「3割は一緒でも失敗した7割のほうに意味があったゆうことですね」
「ついでにゆうとその“3割”にもおかしいところがあると思ってる」
永島のつぶやいた反省に対して、桃が続けて物言いをつけた。
「それもあきませんか!」
永島がまた身構えた。
「いやそんなたいしたことやないねんけど、サモア君のほうは“会っただけで3割”にするんはえらいハードルが低すぎん?」
永島の目が大きく見開いた。
「『お仕事もらった』とか『契約とれた』とかで始めてヒット打ったことになるんちゃう?」
「おっしゃるとおりですわ」
「サモア君の“会えた”ゆうのは、“バットに当たった”ってだけやろ。プロのバッターって『バットに当てるだけでええよ』って話ならなんの準備もせんと10割いけるで」
「僕はバットに当てるだけでもやっと3割やったってことですね」
「残念ながら」
「そんなんで褒められて舞い上がってたやなんて、ホンマに恥ずかしいですわ」
「穴があったら入れたい気分になるよな」
「下ネタやん!」
油断するとすぐにボケようとしてくる桃に、わたしがすかさずつっこみを入れた。
「塔子ちゃんはなかなか見逃してくれへんな」
「逃がさへんで」
「ボケ逃げが出来たとしてもそれはそれで切ないけどな」
「誰にも気づかれへんボケほど悲しいもんはないもんな」
「塔子ちゃんがおってくれて助かるわ」
と、永島のいる日には珍しくなったわたしと桃のやり取りの間も、永島はじっと考え込んでいた。
「どうしたんや、サモア君。なかなかうんこ出えへんのですみたいな顔して」
そっち系のボケは遠慮なくスルーして、わたしは努めて静かに永島の返答を待った。
「いや、社長に褒められてええ気分になってて。ホンマにアホやったなって」
永島は桃が言ったとおり、本当にそれが出ないような顔をして、言った。