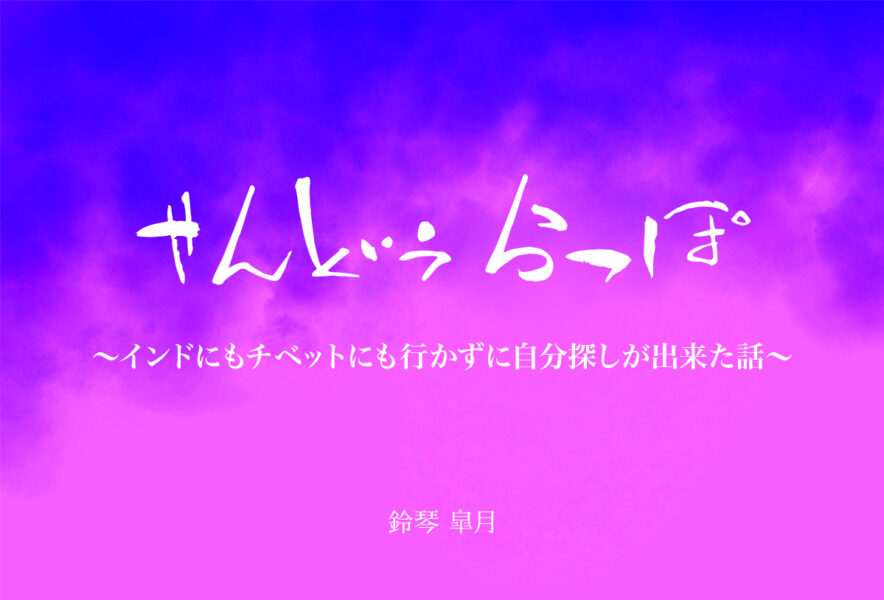「努力の方法が違うってどうゆうことですか?具体的に教えてください、お願いします」
永島はカウンターにぶつける勢いで頭を下げた。
「大丈夫、大丈夫。まだ帰らへんよ。そんな思わせぶりでほっとかへんから」
永島の必死さが伝わったのか、桃も優しく返した。
「サモア君の会社で他にも新規開拓で飛び込みをやらされてる社員さんがおって、その彼にはきちんと結果が出てサモア君になまったく結果が出てないんやとしたら、その差は間違いなく“運”と“タイミング”だけ。そのうちサモア君にも当たりを引く順番が回ってくるよ」
永島は黙って続きを待つ。
「でも魔術師のようなカリスマ営業マンとサモア君のようなダメダメ営業マンの差は、“準備の差”やね」
「準備・・・ですか」
「そう。“運”と“タイミング”を引き寄せる確率を爆上げする“準備”」
しばらく桃と永島の見つめあう時間が流れた。
「さっき飛び込み営業の即興コントした時、サモア君『10回に3回しか会われへん』てゆうてたやん?」
「はい、実際そんなもんです」
「決して効率がええ作業とは言われへんけど、それについては若社長はどないゆうてはんの?」
「『プロ野球選手でも10回に3回ヒット打ったら一流や。裏を返せば7回は失敗するゆうことなんや。みんなも失敗を怖がらずにがんがん飛び込んでこい!』って感じです」
桃は話の途中から眉を寄せて聴いていた。
「その会議の時は珍しく社長から褒められました。『3回も会えるんはたいしたもんや。その調子でがんばれ』って」
「ほう、良かったやん」
桃はわたしから見てもわかるぐらい無感動に、そう言った。
「ぜんぜん良かったとか思てはりませんよね?」
「あ。やっぱりわかる?」
「わかりますよ!」
「こりゃ失敬」
桃はそう言ってからグラスに残っていた黒霧島を飲み干した。
カランと氷の音が心地よく響く。
「でもさっき僕が話してる時に変な表情してはりましたけど、なんかおかしかったですか?」
桃のグラスにおかわりを注ぐわたしを見ながら、永島は桃に尋ねた。
「いや、社長さんプロ野球も好きなんやなぁって思ってただけ」
「絶対ウソですね。でも確かに社長は野球好きですね。大阪生まれの大阪育ちやのになぜか中日ファンです」
「ここ何年かは機嫌悪そうやな」
「シーズン中は最悪です」
「それもあってイライラしてはんのかな」
「もしそうやったら周りは堪りませんね」
「はいはい、野球の話はええから、さっきの続きは?」
嫌な流れを感じたので早めに手を打っておいた。
「ごめんごめん、また話が逸れるとこやったな。で、なんの話やったっけ?『阪神がなんでこんなに強いか』やった?」
「野球から一旦離れて!サモアさんも続き待ってるよ!」
「わかってますやん」
桃は渋々受け入れた。
まったく本当にわかっているのか。
誰かが来店すればわたしは接客の為に一旦この場から離れなければならないのだ。
こうしている間にも今まさに扉が開いて誰かが来てしまうかもしれないのだ。
早く続きを話してくれないとわたしが困る。
「サモア君とこの若社長の野球の話で覚えといて欲しいことがある」
桃が話を再開した。
「はい。中日が負けると機嫌が悪くなる話」
「違(ちゃ)うがな。中日はどうでもええねん。プロでも10回に7回は失敗するゆうほうの話や」
「あ、僕もプロ野球の一流選手と同じ3割バッターやって話ですね!」
永島は褒めてもらえるターンだと思ったのか、ひときわ声が高くなった。
「うん、まぁ大きい括りでゆうたらその話やな」
桃は永島の勢いに若干気圧されたように見える。
ただそう思った次の瞬間、桃は真剣な顔になって言葉を発し始めた。
「準備の話でゆうと、プロ野球の選手ってその失敗した7打席もとんでもない努力と準備をしたうえで、その打席に臨んでるんやゆうことを忘れたらあかん思うで」
「あ・・・」
永島の表情が固まる。
店内の温度が少しだけ、冷たくなった気がした。