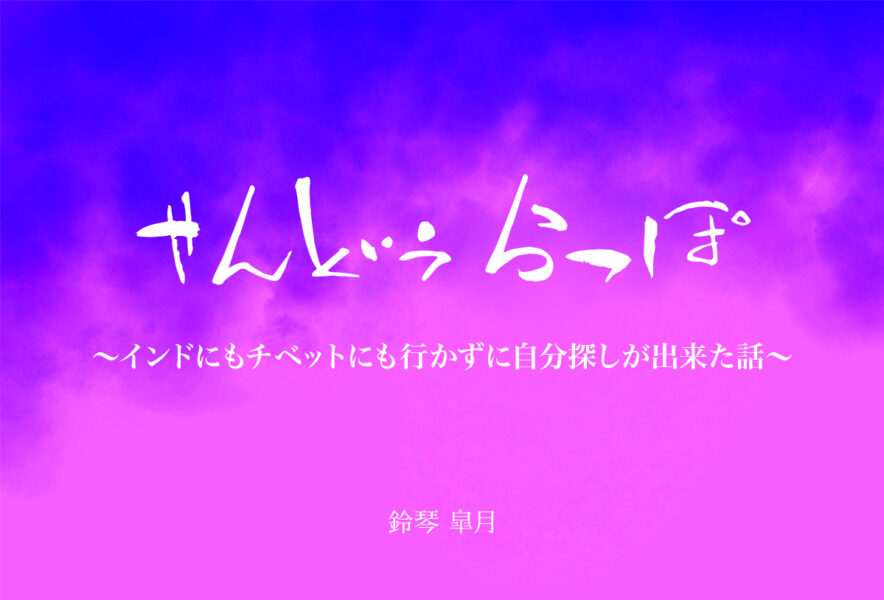「まぁそらあんなん使いこなせたらカッコええよな。本に出てくるカリスマ営業マンはペコペコすることもなく、さっきゆうたような応酬話法を颯爽と使いこなしてスマートに受注していくもんな」
「はい。あんなふうになりたいです」
「ホンマ素直な子やな」
桃は思わず笑ってしまっていた。
ただしかし嬉しそうな笑顔だ。
これも永島が天性で持ち合わせているものが生み出した“緊張と緩和”なのだ。
「あんなふうになりたいんや」
「なりたいです!」
永島が強く言い切った。
「確かにあんな感じで仕事こなせたらまずカッコええし、お客さんと対等な立場っぽいし、何よりめっちゃ楽できるように見えるもんな」
「楽そうやなって思ってるのも事実です」
「そんな真剣なまなざしで“怠けたい願望”をカミングアウトされてもどうしてええかわからんわ!」
桃はまた笑った。
永島と話す時の桃は本当によく笑う。
妬けてしまうほどに。
「使いこなすには条件があるで」
桃は嬉しそうな顔を隠さずに永島に話を続ける。
「条件ですか?」
「そう。条件」
「どんな条件でしょう」
「相手が素人であることと、サモア君が今持ってる “自分の良さを捨てる”こと」
「それが条件・・・?」
「そう。それが条件」
「二つ・・・?」
「とりあえず最低でもこの二つ」
「てか、相手はまず素人でないと使われへんのですか?」
「そうね。もっと詳しくゆうと『ろくに勉強もせえへんのに欲の皮だけが突っ張ってる素人』やね」
「なかなかパンチの効いた素人ですね」
「あとは人の良さそうなお年寄り、とかもええかもね」
「素人の・・・?」
「そう。素人の」
「なんか・・・。騙す前提・・・?」
「おおっ、さすが!ええとこに気づいたね」
「だって桃さんのゆうてはる“素人”って、詐欺のニュースとかで絶対出てくる被害者さんですやん」
「そやで。騙せやすそうやろ?」
「騙すって・・・」
永島は絶句した。
ここまで桃に対して懐疑的な目を向けた永島は初めてだった。
「桃さん、すいません」
永島はしばしの沈黙のあと、気を取り直したように桃に話しかけた。
「わかってくれてはるとは思いますけど、僕は別に詐欺師になりたいわけやないです」
悲痛な叫びとも取れるような、永島の訴えだった。
「そうね。もちろんわかってるよ」
桃は笑顔で、優しい声で言った。
「サモア君が詐欺師志望でないこともわかってるし、応酬話法を使(つこ)てはる人がみんながみんな詐欺師やてゆうてるわけでもない」
永島は黙って桃を見る。
「もしサモア君が応酬話法を使って通用するとしたら、相手はそうゆう系の素人さんしかおらんよって話」
桃は優しい表情を崩さないまま言った。
「素人以外には僕に使いこなすことは無理ってことですか」
永島がまた沈んだ声になる。
感情の起伏がジェットコースター並みなのは彼の通常運転だ。
「応酬話法ゆうのはな」
桃の目から優しさが消えて真剣モードに代わった。
「応酬話法は基本的に相手をコントロールする為の手段やゆうことを忘れたらあかん」
「コントロールする・・・」
「そう。自分の思う通りに相手を誘導するゆうこと。本にもそない書いてあったやろ?」
「そうですね。そんな感じの説明が多かったです」
「それが応酬話法」
「それが応酬話法・・・」
「そやで。失礼やと思わんか?」
「失礼?」
永島が聴き返した。
「そや!おれのことを言葉ひとつでコントロールできる人間やと思てるゆうことやろ!」
「桃さんにはさすがに通用しなさそうですね」
「たまにおるねん。訪問販売とか家電量販店とかにおる兄ちゃんで」
「あぁ、おりそう」
「『これ欲しいけど高いなぁ』『そうです、高いですよね。でもねお客さま・・・』とか“イエス-バット”の“イ”が見えたぐらいでどんなけ欲しても『やっぱりいらんわ!』ゆうてすぐ帰ったんねん」
「早っ!」
桃の一人コントにわたしがすぐさまつっこみを入れ、しばし三人は笑い合った。
が、しかし永島のそれは明らかに固くぎこちないものであった。